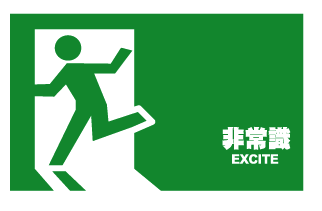社長の息子二人、長男の野地伸卓(のぶたか)と次男である良成(よしなり)が野地木材工業(現nojimoku)に就職して13年が過ぎた。
二人が入社した当時、生産拠点はいまの本社工場だけで、そこで製材と加工を行い、主に東海地域の製品市場、問屋に商品を降ろしていた。今では協力工場3社を含め、この熊野地域で9カ所の拠点で活動している。北は北海道、南は九州と、日本全国に商品を発送するようになった。
客観的に考えて、住宅着工数が減り続け、製材所の取り巻く環境は年々悪化し厳しくなってきている中、おまけに日本のチベットと呼ばれるような熊野という僻地 of 僻地は、消費地から遠く離れ、配送コストが高くつき、フットワークも不利。そんなところで製材を行い、全国へ販売していこうという考えが、そもそも誰が見てもおかしいと思うのは明らか。
社長である野地洋正(ひろまさ)は、いったい何を考え、なぜ息子二人を呼んだのだろうか。
2002年、当時、洋正の息子三人は東京都杉並区の永福町に住んでおり、兄弟で三人暮らしをしていた。伸卓は洋正の母校でもある高千穂商科大学(現 高千穂大学)を卒業し1年が経っていたが、どこにも就職せずゲームセンターでアルバイトをしながら、ロックバンド活動にのめり込んでいた。
良成はデザインの専門学校に3年間通い卒業した後、彼も伸卓と同じくバンド活動しながら、メキシコ料理屋のアルバイトで生計を立てていた。二人は高校の時に結成したバンドに所属し、伸卓がギターボーカル、良成はドラム、そして伸卓と高校の同級生で、”中島らも”に顔が似た白木(しらき)という男がベースを担当し、3ピースのバンドを東京でも続けていたのである。三男の陽介(ようすけ)もまた高千穂商科大学に入学し、当時はまだ2年生で、彼もフォークソング研究会に在籍し、音楽にのめり込んでいた。
彼らが東京で音楽にのめり込んだ背景には、熊野というTHEど田舎で、製材業を営み、毎日オガまみれになって一生を終えることほどくだらない人生はない、という考えが根底にあり、熊野から逃げるように製材業とは真逆の生活を夢見て東京に出てきていたのだった。
当然甘いものではなく、また、音楽の才能が特段飛び抜けてあるわけでもない兄弟は、ただただ東京で酒とロックを浴びる毎日を過ごし、意味も特別な想いもなくダラダラと暮らしていた。
ただ、そんな彼らも、自分たちの作る音楽にはある一定のこだわりがあった。そのこだわりとは、万人に売れるための音楽を作るよりも、自分たちの納得するクオリティの音楽を作りたい。その自分たちの納得するクオリティとは、わかる人にはわかる音楽、叙情的な詩をポップなメロディーに乗せ、サイケデリックなサウンドをシンプルに3ピースバンドで奏でたい。そして少数でもいいからこんな僕らを特別と感じ、喜んでもらえるような音楽を作りたい。彼らはそんな自分勝手な自己満足を”こだわり”と呼んでいたのだ。
彼らのバンドと一緒に同じ時期に活動していたバンドの中から、プロデビューを果たしたり、後に紅白歌合戦にまで出場するようなバンドもいた。しかし伸卓は自分たちより先に売れていくバンドを見ては「くだらない音楽で売れて楽しいのかねぇ」とバカにし、誰からも注目されない本当にくだらない陳腐な音楽は自分たちの方であるということに一向に気付かぬまま、ひたすら酒に酔わされる日々を送っていたのだった。
彼らはそんな中で、月に一回ほどのペースで新宿や渋谷近辺のライブハウスで活動をしていたのだが、ある日のライブ終了後の打上げ中、居酒屋で酒を飲む伸卓の元に一本の電話がかかってきた。
「もしもし?伸卓?」
伸卓の母、真美(まみ)からの電話だ。普段は実家から滅多に電話などかかってくることがない。3ヶ月ほど前、年末年始を実家で過ごすために熊野に帰ったがそこでも特段たいした会話など交わさなかったので、なんだろうと不思議に思いながら電話に出た。
「ん?あ、もしもし。なに?どしたん?」
「あんた今なにしとるん?」
普段通りの母の声。大変な事件か何かが起こっての電話なのかという不安はとりあえず無用そうで、伸卓はホッとした。
「今日はライブやったからね。終わっていま打ち上げしとるよ」
「ふーん。あそう。」
「んで、なに、用事は?」
さっさと電話を済まして、ビールで喉を潤したい伸卓はぶっきらぼうに返事をした。
「いや、あのさー、最近お父さんがね、あんたらにめっちゃ帰って来て欲しそうな空気をどいらい出すんさ。言葉には出さんけど、空気がどいらいんやよ。そろそろもう、帰ってこんし。え?」
真美は衝撃的な言葉を伸卓にぶつけた。
“帰ってこんし”
伸卓はその言葉を初めて母親の口から聞いた瞬間、それまで楽しく飲んでいた酒の酔いが一瞬で冷めた。目の前の情景はすべてモノクロに見え、音声がまったく耳に入らない、そして呼吸をすることすら忘れてしまいかねない、そんな呆然とした顔になった。
そして伸卓は、ほぼほぼ無言で電話を切ったのだった。
「ついに来た。これが赤紙を受け取った青年の心境というものだろうか。。。」
不思議と思ったほどの拒絶感は感じないが、恐怖というか、不安というか、東京とバンド活動からサヨナラする事への虚脱感というか、過去に体験した事のない心境の中で、伸卓は初めて生ビールを飲み干す事なく、居酒屋を後にした。
つづく。

-
2023.04.30 Sun/ writer: 野地伸卓第5話 ゼットの呪縛
-
2017.09.02 Sat/ writer: 野地伸卓第4話 業界の常識
-
2017.03.06 Mon/ writer: 野地伸卓第3話 洋正と真美
-
2016.08.26 Fri/ writer: 野地伸卓第2話 しゃぼん玉
- nojimokuで働くってたいへんですよね? ノンフィクション~社員たちの本音~ (5件)
- おもしろさ、ふつふつ。 (4件)
- お知らせ (26件)
- ソトノノノプロジェクトwith近畿大学 (2件)
- トピック (107件)
- のじもくインターン生のブログ (13件)
- のじもくツアー (10件)
- ゆかいなコンテナプロジェクトwith武蔵川女子大学 (1件)
- 木宰治のウッドバイ (5件)
- 木材 (5件)
- 熊野こどもだいがっこう (10件)
- 社長ブログ (8件)
- 遊木の改修プロジェクトwith早稲田大学 (23件)